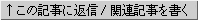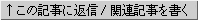:23
◆ 題名: 住民参加条例委員会2004/03/25公開意見
住民参加条例専門研究委員会参加委員によるこの委員会自体の自主評価
2004年3月25日委員会 送付提出意見
公募委員 大木正美
こういう審議会は二度と再びあってはならない。
「愛川町の住民参加」が育っていく上で。
十分すぎる反面教師である。その意味で大きな「負の礎」にならなければ意味がない。
平成14年度第2回・第3回委員会で、町各課の住民参加状況「現況調査票」報告が示された。
各課共「審議会応募者がすくない。」「説明会参加者が少ない。」という課題認識と評価が大半を占める。
では将来に向けてどうするか。
後に行政側としてのソリューション(自己解決策)が整理・提示された。
審議会自体の自己評価、参加者アンケートの必要性・フィードバック(反映前進)姿勢も示されている。
そして今回のこの委員会も終わりには「自己評価をしましょう」ということも事務局自らの発言で示しておられ、委員会の申し合わせ事項になっていると記憶している。
私自身の委員としての自分自身に対する自己評価とともに、
(Q)この委員会総体の自己評価を今後どうなされるのか?
↑これは明解に質問事項として、まずここで記して置きます。(文脈上位置が乱れますが)
同じ質問は、参加者各自への問いかけでもあります。前回もこの呼ぶかけをしました。
この参加経験と評価を適格に未来に反映させていってこそ社会としての前進があります。
-------------------------------------------------------------
さて、まず自分自身への自己評価ですが、
自己弁護になりますが、所詮シロウト。かつ委員会自体のユーモア(人間的ゆとり)感がなく、議事進行も対話感、議論感がまったくなく、どんどん自己閉鎖していく感でした。
次に、冒頭、「こういう審議会は二度と再びあってはならない」と評価した各論。
・審議会冒頭、委員長選任儀式:
なぜ「委員長」を答申者町長名自身で指名しないのか?
参加者一部委員の口を借りて推薦し、なおかつ「異議なし」の声を借りて会総体の選任とする儀式はいかがなものか?
猪木委員などマスコミをにぎやかした道路審議会も委員長は首相が指名しているのではないか?
住民参加手続きを演出したかのような、しかし、最初からシナリオで始まりシナリオ通りに終わる儀式と一般住民参加者に印象させる十分余りあった、まったく逆効果明白。
・委員長議事進行:
スケジュール管理に没頭して、ことあるごとに「時間通りの進行に協力を!」と再三再四の投網で、発言者に強力な無言の圧力感。
新聞報道では、「取りまとめた」という評価のとらえかただが、その評価はすべて選任者側の時間管理において仕切ったという評価でしかない感。
参加者側からの評価があってはじめて社会的評価であろう。
不規則発言や本題を反れた発言を制し議論が深まる議長役進行がなされてはじめて評価される役であるはず。
また、こういう住民参加、ワークショップとして呼ぶかけられたような委員会に必要な取りまとめ役は「コーディネーター」、あるいはその資質あってその役割認識もあるものが通常である。こういう委員長に与えられた職務自体が「住民参加」資質の常道をはずしている。
・顧問講師:
同上、いかにコディネーター資質をもっているかに大きく欠ける。
住民側ほとんどシロウト、(職員とてシロウトに毛が生えた程度が大方と思われる)相手に説明の下手さは余りある。「こういう用語は説明が難しい=置き替えられない」というような説明発言を再三平然とされている。
プロ同士の講義の場なら済ませられる知識資質評価があるとしても、住民参加をシロウトと論じ合う、理解の一助となるべき立場の能力としていかがなものか?
・事務局:事前に読み込まなければならない資料を参加者に送付する時間的余裕のなさの感覚は職怠怠慢すれすれとさえ思われる。(もちろん前提としてそういう忙しいスケジュール管理が問題原点であろうが)
当初議事録さえを参加者から促されなければ配布準備もしておかない感覚的ルーズ。かつ、作成された議事録にいかに議事内容を正確に残そうかの観点欠如のデモクラシー根源に欠ける感覚。
以上、目だった一部のみの感想列記ながら、まとめて再度、
こういう審議会・委員会は今後二度と再びあってはならない。