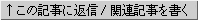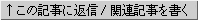◆ No, 11
◆ 氏名:(仮名に変更) (53 )
◆ リンク:http://loveriver.net/e-democracy/
◆ 日付:2002.9.12(木) 03:23
◆ アクセス:31
|
:19
◆ 題名: 住民参加〜(委員会提出)意見
(仮称)住民参加条例制定に係る専門研究委員会(第2回)一般公募委員 提案意見感想原稿
1.(住民参画の現況と課題) 『住民参加条例制定に係る現況調査票』資料について
2.(自治会の現状)区長と行政嘱託員兼任制度について
意見発言:8月12日・9月3日
原稿文書提出:9月3日(第3回時)
(仮称)住民参加条例制定に係る専門研究委員会(第2回)一般公募委員提案意見感想原稿
今回、議題の「本町における住民参画の現況と課題について『住民参加条例制定に係る現況調査票』」
資料を事前にいただき、目を通しました。
感想ほか、議事進行について、ぜひ今の時期に申し上げておかなければならないのではと思いました。
また私の疑問的感想に対して、参加の皆さんはどう思われるか?その議論を起こしたいと思います。
まずこの資料は、すべて現状の問題点・課題の羅列をしている「報告」です。
が、もしこれが「民間」の会議だったとしたら
・現状と問題点は出ている、
・参加者が少ないとかうまくいってないことが羅列されている、そして、
・ (アンケートも出ているように)お客さまのニーズもわかっている・・・
・・・なのに、「なぜ少ないのか」、「ではどうしたらいいか」、「今後業績を上げるにはどのように
したらいいか」、 そういう方針案・展望のひとつも記されていない、(その記述欄さえない書式の)
「報告書」などというのでは、民間経営感覚では「何のために会議している!」と社長の大目玉を食ら
うことでしょう。
民間ばかりではなく、官業の、例えば警察の(捜査)会議などで、もし「現状はかばかしくない、で
は今後こういう方向に重点を置きたい、こういう展望の可能性がある」と、各担当者が有益な捜査方針
も持ち寄らない会議を重ねていたら、どんな優秀なチームを組んでいようと、進展・成果は何も得られ
ません。
もちろん、この(仮称)専門研究委員会はその一つ一つの問題点を検討論議する場ではなく、そうい
うプロセスの報告を受けながら大きな理念方針をまとめつくりあげていく会議であろう と思います。
ただ、数行の箇条書き欄でいい、「なぜか」「ではどうしたらいいか」という行政各課のお膝元のア
イデア論もない・・・ そうして、出来上がっていく「条例」とは、「コトバはまとまったが中身はあ
りません」となる前兆を表しているほかないと言えませんか?
名前こそは、(当初私たちには)「ワークショップ」と呼びかけられていたものから「専門研究委員
会」と仰々しく呼ばれるようになりましたが・・・
次に、「愛川町における住民参画の現況」の報告の中で、第3項め、アドバイザー・行政課題調査研究
員の感想として「区長又は地区嘱託員が関連する事例が多数見受けられ、本町における住民参加施策に
大きな役割を担っている」ということがあげられています。
この「自治会の現状」として「大きな役割」を担っている、「区長・地区嘱託員兼任」の現状につい
ては、他の現況調査票とひとまとめに説明資料とされていますが、これについては、他のような「問題
点・課題」の視点の取り上げられ方・記載もされていないわけです。
今、私が、語弊を恐れず、率直に言えば「だからダメなんだ」と言い添えたいと思います。
問題はあるのです。きちんとアンケートをとれば聞こえてくる問題はあるのです。
何が問題かということを以下で記しておきますが―――
特に今、これから住民参加条例をつくろうという時代的理念と、この区長・地区嘱託員兼任というシ
ステムにみる考え方は、もはや絶対的論理矛盾で、同時代に共存し得ないのではなかろうかと。問題提
起の一例として。
この地区嘱託員制度の要綱が作られた日付を見て驚きました。昭和32年という、被占領日本が自治主
権を取り戻して5年たらず、いわゆる「現在の愛川町」に合併された直後、人口わずか1万人程の時代に
つくられたものです。(もちろんこの時の町村合併に、現在のような地方分権とか住民参加といった理
念は付いてなく、おそらく中央統治の考え方一色だったのではと思いますが、行政嘱託員制度というの
はどこかしこにも存在したようなので、)おそらく中央自治省指導があったのかも知れないし、当時の
時代背景含め地方自治専門でおられる辻先生の解説とか見解もお聞きしたい。ちなみに「住民参加」と
いう用語がはじめて広辞苑に登場したのは昭和58年)
この「住民参加」テーマに大きく登場する、区長・行政嘱託員兼任制度は、もう時代物だというだけ
でなく、これから「(いわゆる)老害問題」にもなるのではなかろうか?
(今回の一般公募委員の選考面接でも、「自治会に入っているか」、「積極的に参加しているか」とい
うような項目質問をされましたが、そうたずねる方においては、それが基本的なことと信じているんだ
ろうなーと思いました。ギャップは感じました。)
例えば、地区嘱託員設置要綱第5条3に、職務のひとつとして「地域住民の要望・意見の取りまとめ」
とありますが、これは「住民ニーズによって住民自身のため」のものであって、なにも「とりまとめて
くれ」と町が頼むものではなく、住民自身が自立的に積み上げて町へ届けてこそがこれからの住民参加
の基本的理念であろうと。
報酬が出るとしたら、当然住民組織の「自治会」から出るのが本筋であって、自治会の会計上苦しい
と言うのであれば、自治会に助成なり補助をする考え方が適当では。
もちろん、金額も各自治会の中での自由な取り決めであっていいし、一律にどうこうしろというもの
でもない。「あの金額でよく一生懸命やってくれている」とか、「あれだけもらっていのに、あのくら
いのことしかしない」とかの評価も自治会住民の内部評価の裁量のものだろうと。
次に「町行政の一員」としての職務と言うのが列記されていますが、これも別に区長でなければなら
ないと固定的に考える必要がない。区長であってもいいし、他の人でもいい。線で引いた行政区単位に
固着する必要もない。(とくに最近はNPOへの職務委託としてもおかしくない範疇の時代になってきてい
る。)
「自治会・区長とは関係なく、『個人』として頼んでいる」と町はそういう見解を取っているようです
が、個人ならなおさら、他の個人でもいい。また個人なのだから「その職務だけ個人的に断わる」とい
う自由な選択肢があってもいいはず。
例えるなら、(適当かどうかより、ただ、小学生にもわかるような例えとして、)「学級委員長に選
任されたら、トイレ掃除係りも込みでやらなくちゃいけないことになった」というようなもので、役に
つく皆さんはそれぞれ使命感でやられていると思いますが、選任されたプロセスと違うところから報酬
と職務義務、というセットでは、高齢化傾向の時代、負担感ばかり大きくなるのでは。
このベースにある「要綱」という決まりごとの性格については、前回辻先生の講義でようやく知った
ような次第ですが、こういう自由な裁量に欠ける決まりごとが、住民参加とは一番程遠いところで決ま
っている、というのも首を傾げるところです。
自治会に入る入らないは(基本的考え方としては)決して義務として強制されるものではありません。
住民の自由な立場の積み上げの上にあるべきはずの、その任意参加自治会の上の方の役職と町との関わ
りになると、本来使命感の自由あっての役割に、なかば強制的な義務として固定的な職務に配置される。
こういう考え方は、これからの住民参加の考え方とは相容れない、時代として共存し得ない、と。
そういう自由な前提でこそ何ごともはじめて真に「参加」を楽しめるのではないか、そういう気持ち
は皆さん体験されていないか、どう思われるか、とお伺いしてみたいのです。
また、住民参加現状がはかばかしくないことの認識がありながら、こういう各地区ごとに行政のいわ
ばお抱えの一員がいるということで、説明会や意見交換会といった住民主体で開催されるべき時に、給
料払っているんだからと、ここぞとばかり客集めとして行政側が頼る、言われた方は職務だから「ノル
マをこなす」と・・・ そういう繰り返しの根底があるから、低調な延長ばかりで、新しい展開がない
のではと。
民間の催し物・集客手法など、見習うべきサービス産業的発想は良いサンプルがころがっています。
「必ずうまくいかなければいけない」という呪縛から逃れて、いろいろやってみるべきものはあります。
そういうサービス業の感覚のなかでいろいろな提案を出していきたいと思いますし、またそういう持
ち寄りが自由に忌憚なく話し合われていくのが、時代の「審議」という語義だと思います。
平成14年8月12日
|
|